はじめに:介護費用、どこから出す?
介護が始まると、多くの家庭が直面するのが
「介護費用をどこから出すのか?」という問題です。
親の年金?貯金?それとも家族で分担?
感情とお金が交わるテーマだからこそ、
冷静に「仕組み」と「優先順位」を知っておくことが大切です。
① まずは「親自身の収入」を把握する
介護費の主な原資は、まず親自身の収入から考えます。
代表的なのは以下の3つ。
公的年金(老齢基礎年金+厚生年金など)
企業年金・個人年金
預貯金・退職金の一部
💡 目安:
70代の平均年金受給額は約14〜17万円/月(単身者の場合)。
この中から生活費を差し引いて、残る分を介護費に充てます。
まずは「毎月いくらの余力があるか」を可視化するのが第一歩です。
② 不足分は「家族で話し合って分担」
年金だけでまかなえない場合、
家族でどう補うかを話し合っておきましょう。
補い方の例:
毎月の費用を家族で分担(子ども2〜3人で割る)
大きな支出(入居費用など)は一時的に援助
施設費用の一部を親の資産から引き出す
💡 大切なのは「誰がどの負担をするか」を明確にしておくこと。
あとで揉めないためにも、事前にルールを決めておくのがおすすめです。
③ 「介護費を助けてくれる制度」を活用する
足りない部分を補うために、
次のような公的支援制度も活用できます。
| 制度名 | 内容 | 申請先 |
|---|---|---|
| 介護保険 | 自己負担1〜3割で介護サービス利用可 | 市区町村 |
| 高額介護サービス費制度 | 自己負担上限を超えた分を払い戻し | 市区町村 |
| 介護保険負担限度額認定制度 | 所得に応じて食費・居住費の減額 | 市区町村 |
| 医療費控除 | 介護・医療関連費の一部を確定申告で還付 | 税務署 |
制度を知っておくだけでも、実質的な負担が数万円単位で変わることがあります。
④ 「親のお金」をどう管理するかを決める
介護が長期化すると、お金の管理方法が重要になります。
選択肢としては:
家族の誰かが「代理人」として手続きを行う
成年後見制度を利用する(判断力が低下した場合)
銀行口座をまとめておく(複数口座の把握)
💡 トラブル防止のために、
通帳やカードの「管理担当者」を1人決めておくとスムーズです。
おわりに:話しづらいお金こそ、早めに話す
介護とお金の話は、気まずくて後回しになりがち。
でも、準備しておくことで家族全員が安心できるテーマです。
「今のうちに少し整理しておこうか」
そんな一言から始めるだけで、将来の負担は大きく減らせます🌿

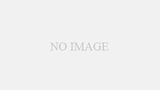
コメント