はじめに:介護は“ある日突然”始まる
「昨日まで普通に暮らしていたのに、急に入院して介護が必要になった」
──そんなケースは決して珍しくありません。
いざ介護が始まると、
役所・病院・保険・職場など、
短期間で多くの連絡と手続きが必要になります。
この記事では、介護が始まったときに慌てないための
「やることリスト」と「連絡先」を分かりやすくまとめました。
① まずは「介護保険の申請」を行う
介護サービスを利用するには、
要介護認定の申請が必要です。
📝 手続きの流れ
親の住所地の市区町村役所で申請
「介護保険被保険者証」を提出
自宅に訪問調査(約1〜2週間後)
判定結果が郵送で届く(約3週間後)
💡 申請に必要なもの
介護保険証
医師の診断書(主治医の意見書)
印鑑・身分証
申請は家族でも代行可能です。
「地域包括支援センター」に相談すれば手続きも代行してくれます。
② 医療機関・かかりつけ医への連絡
介護が必要になったきっかけが病気・けがの場合、
医療機関との連携が欠かせません。
チェックポイント
退院時に「退院時サマリー(診療情報提供書)」をもらう
主治医に介護保険申請のための意見書を依頼
ケアマネージャーに情報を共有
💡 退院前カンファレンス(家族・医療・介護の3者面談)を開くと、
スムーズに在宅介護へ移行できます。
③ 職場や学校など、家族の関係先にも連絡
家族の介護が始まると、
仕事や家庭の予定に影響が出ることがあります。
早めに伝えておくことで、
柔軟な対応や休暇制度を利用できる可能性があります。
伝えておきたい先
勤務先(介護休暇・時短勤務など)
子どもの学校(家庭状況の共有)
地域の民生委員・近所のサポート者
💡 介護休業制度を利用すれば、
最長93日間の休業が可能(雇用保険加入者対象)。
④ 公的手続き・給付金の確認
介護が長期化すると、経済的負担も大きくなります。
利用できる公的支援制度を早めに確認しておきましょう。
| 制度 | 内容 | 窓口 |
|---|---|---|
| 高額介護サービス費制度 | 介護費の自己負担上限を超えた分が返金 | 市区町村 |
| 高額医療費制度 | 医療費の上限を超えた分が返金 | 健康保険組合・国保 |
| 医療費控除 | 医療・介護費の一部を確定申告で還付 | 税務署 |
| 介護保険負担限度額認定制度 | 食費・居住費の軽減 | 市区町村 |
💡 **「何が申請できるか」**を、包括支援センターで一括確認すると早いです。
⑤ 介護が始まったらやっておきたい家族内の共有
介護が始まると、情報共有のミスがトラブルを生みます。
家族で共有しておきたい項目:
医療・介護の連絡先一覧(病院・ケアマネ・施設など)
親の希望や要望(医療・生活・金銭面)
費用の分担・支払い方法
💡 ノートやLINEグループで共有しておくと、
家族全員がいつでも確認できます。
おわりに:準備しておくほど“心の余裕”が生まれる
介護の手続きや連絡は、
初めてだと誰でも戸惑うものです。
でも、「何をすればいいか」を知っておくだけで、
焦らず落ち着いて対応できます。
もしもの時に慌てないために、
今のうちに“連絡先リスト”だけでも作っておきましょう🌿

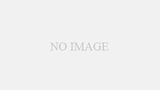
コメント